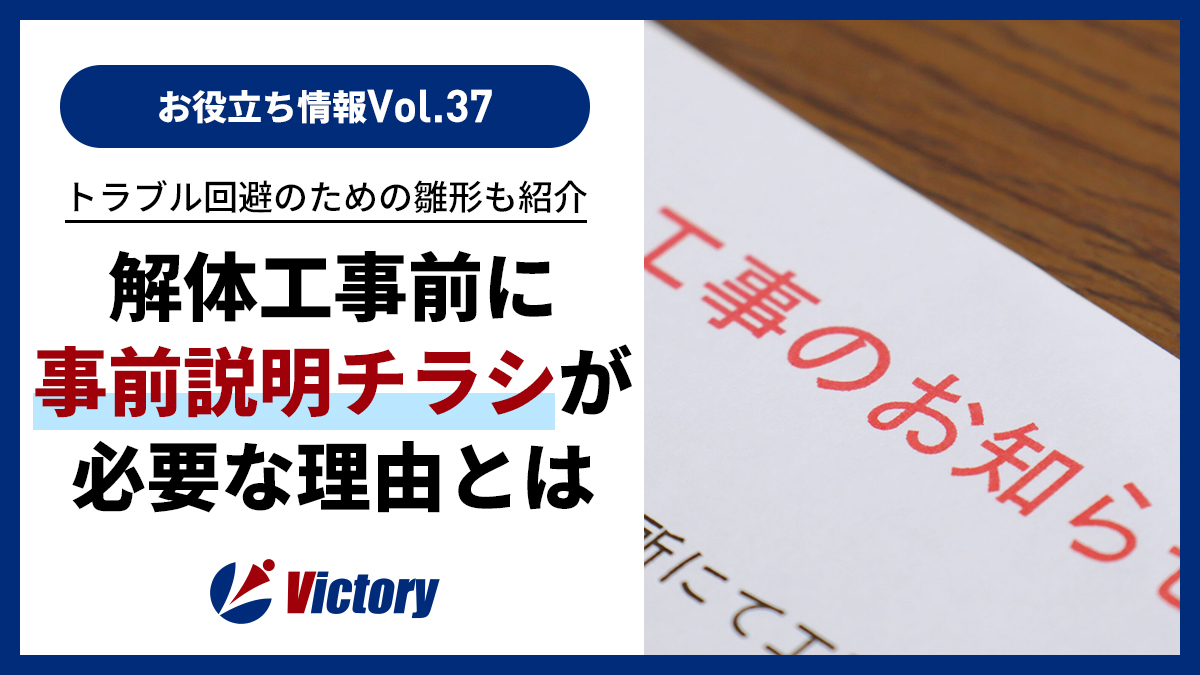住宅解体の残置物処分方法は?片づける範囲や処分方法などを徹底解説

住宅を解体するとき、多くの人が悩むのが「残置物の処分方法」です。家具や家電、日用品が残ったままでは工事が始められず、追加費用やトラブルの原因にもなります。しかし、具体的にどうすればいいかわからず困っている人も多いのではないでしょうか。
お電話でのご相談
平日 8:00-18:00
最短即日対応◎メールフォーム
そこで本記事では、残置物の定義から処分方法、法律の方針や注意点を徹底解説します。これから住宅解体を控えている人の参考になるため、ぜひご覧ください。
住宅解体の「残置物」とは?定義と範囲

残置物とは、建物本体や附属設備を除いた「生活で使用していた物品」のことです。環境省のガイドラインでも、残置物の適正処理を施主側が行うことを求めています。ここでは、住宅解体における残置物の定義と範囲を解説します。
残置物の具体例
住宅解体の際の残置物には、以下のようなものが含まれます。
- 家具(タンス、ベッド、机など)
- 家電(冷蔵庫、洗濯機、エアコン)
- 生活用品(衣類、食器、本、布団)
- 自転車や庭の遊具
これらは「家の解体で残してよいもの」と誤解されることがあります。しかし、基本的には住宅を解体する前にすべて撤去しなければいけません。特に、粗大ゴミや家電リサイクル対象品は適切に処分しなければ法令に違反するため、注意が必要です。
建材・附属設備との違い
残置物と建材・附属設備は、明確に区別されます。壁や窓、風呂釜やキッチンにエアコン本体などの建材や設備は、建物の一部とみなされるため解体工事に含まれます。一方、家具や私物は施主が処分しなければなりません。
例えば「家の解体でタンスを置いたままでも良いか」という疑問がありますが、タンスは残置物に分類され、基本的には撤去が必要です。撤去に特殊な工事や作業が必要となるものは建材となると認識しておくと、残置物との区別がしやすくなります。
法令・行政の考え方

環境省は「残置物の適正処理のお願い」リーフレットを公表し、残置物は施主側が処理することを明確化しています。ここでは、残置物に関する法令や行政の考え方を解説します。
誰が片付けるべきか
残置物の片付けは、解体する住宅の所有者が責任を持って行うのが原則です。解体業者に依頼することも可能ですが、その場合は追加費用が発生します。そのため、解体業者に残置物の処分まで依頼すると、余計な費用を支払わなければいけません。
POINT
金銭的な理由を踏まえて、解体業者が産業廃棄物として処分するのではなく、施主が一般廃棄物処理業者に依頼するのが基本です。残置物処理を怠ると工期が遅れたり、契約トラブルになる恐れがあるため、注意が必要です。
一般廃棄物と産業廃棄物の線引き
残置物は基本的に「一般廃棄物」に分類され、市区町村の処理ルールに従う必要があります。一般廃棄物は、家庭から出るいわゆる家庭ごみや事業活動に伴って排出される産業廃棄物以外のものです。
一方で、解体工事中に出る瓦礫や建材は「産業廃棄物」として扱われ、解体業者が処理を行います。一般廃棄物の中でも、冷蔵庫や洗濯機は一般廃棄物ではなく「家電リサイクル法」に基づいた処理が必要です。環境省も明確に区分を示しており、適正に処理しなければいけません。
どこまで片付ける?引渡し基準の決め方

残置物をどこまで片付けるかは、契約内容や解体業者との取り決めによって決まります。ここでは、残置物をどこまで片付けるか、判断するポイントと契約時の注意点を解説します。
どこまで片付けるか判断ポイントと優先順位
残置物を処分する際、どこまで片付けるかは以下の基準で判断するとスムーズです。
- 家具・家電はすべて撤去
- 衣類や生活用品も撤去対象
- 庭の物置や自転車も処分
POINT
一方、建物に固定された窓や扉、水回りなどの設備は業者が解体時に撤去します。施主側で迷う場合は、業者に確認してから処分範囲を決めるのが安全です。「自分で処分できるものは自分で処分する」と考えれば、片付ける範囲を判断しやすくなります。
契約書の残置物条項・立会い・写真記録
住宅解体の際の残置物の範囲は、解体業者との契約書で明記し、立会いや写真記録を残しておくことが重要です。解体前に「残して良い物」「撤去が必要な物」を確認し、証拠を残すことでトラブル防止につながります。
こうした取り組みは環境省もリーフレットで適正処理を推奨しており、施主・業者双方の合意形成を明確にできます。万が一、何かトラブルが起きた際に解決するための重要な資料となるため、契約書は工事が完了するまで保管が必要です。
残置物の処分方法

住宅解体で発生する残置物は、仕分け、処分先の選択、搬出の3ステップで対応が必要です。効率的に進めることで費用と時間の削減につながります。ここでは、それぞれの段階を詳しく解説します。
仕分け
住宅解体をはじめる前に、まずは残置物を仕分けます。家具や家電、日用品を種類ごとに分け、リサイクル可能な物と廃棄物を区別します。特に、冷蔵庫や洗濯機など家電リサイクル法対象品は、一般廃棄物として処分できないため注意が必要です。
POINT
また、灯油やガスボンベなどの危険物は、別途専門業者が必要になるケースがあります。解体工事の直前に慌てないように、早めに仕分けることがスムーズに解体をすすめる第一歩です。
処分先の選択
仕分けが終わったら、残置物の処分先を決めます。選択肢は大きく分けて3つあります。
- 市区町村の粗大ゴミ収集や清掃センターを利用
- リサイクルショップや買取業者に買取を依頼
- 解体業者に残置物処理を委託
環境省の指針では、残置物は施主による適正処理が推奨されています。そのため、住宅解体の際に発生する残置物は、可能な限り自分で処分するのが基本です。ただし量が多い場合や大型品は、専門業者への依頼を検討しましょう。
搬出・運搬
処分先を決めたら、住宅から搬出して運搬します。家具や家電は重量があり、人手や車両を手配しなければ搬出できません。階段のある住宅では特に危険が伴うため、解体業者や不用品回収業者のサポートを活用するのも有効です。
注意点
運搬時には道路交通法や市区町村のルールに従う必要があります。無理に自分で運ぼうとすると事故や追加費用につながるため、慎重に計画して運搬することが重要です。自分で運搬するのが難しければ、業者への依頼を検討してみてください。
品目別:残置物の処分方法と注意点

残置物は品目ごとに処分方法が異なります。ここでは、以下の品目ごとに処分方法と注意点を解説します。
- 家具(タンス・ベッド等)
- 家電
- 危険物(灯油・塗料・バッテリー等)
- 書類・写真・仏壇など
家具(タンス・ベッド等)
家具は基本的に粗大ゴミとして処分します。市区町村の収集サービスを利用するか、清掃センターに持ち込み、処分が可能です。リユースできる家具はリサイクルショップや寄付を検討すると処分費用を削減できます。大型の家具は運搬に手間がかかるため、出張買取や引取をしてくれる業者を探して依頼すると、スムーズに処分できます。
家電
家電の処分には注意が必要です。特に、冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンは家電リサイクル法の対象で、市区町村では回収できません。販売店に引き取りを依頼するか、指定引取場所へ搬入が必要です。その他の小型家電は自治体の回収ボックスを利用できます。家電も家具同様にリサイクルショップなどで売れる場合があるため、利用を検討してみてください。
危険物(灯油・塗料・バッテリー等)
灯油や塗料、バッテリーやガスボンベなどは一般廃棄物として処分できません。なぜなら、火災や爆発のリスクがあるためです。そのため、危険物は必ず専門業者へ処分を依頼しなければいけません。危険物は、自治体や販売店で引き取りサービスを実施している場合もあるため、利用できないか調べてみてください。
書類・写真・仏壇など
個人情報を含む書類は、シュレッダーや溶解処理サービスを利用すれば確実に処分できます。写真や仏壇など思い入れのある品は、供養やお焚き上げを行うことで心情的にも整理がつきやすくなります。思い入れのある品は、感情面を考慮した処分方法を選びましょう。
回収業者・遺品整理・解体業者など依頼先の選び方

残置物の処分を依頼する場合、目的に合わせて業者を選ぶことが重要です。不用品回収業者は大量の家具・家電の処分に便利で、即日対応もできます。遺品整理業者は、故人の遺品や思い出の品を丁寧に仕分けたい場合に最適です。
POINT
解体業者にまとめて依頼する方法もありますが、別途費用が発生するため契約前に明細を確認することが重要です。信頼できる業者を選ぶには、許可証の有無や口コミ・実績を必ず確認しましょう。
建物解体で残して良いものとNGなもの

解体工事では「残して良い物」と「撤去すべき物」があります。残して良い物は、ブロック塀・庭木・井戸など施主が保存を希望する品や設備です。ただし、残す場合は工事の支障にならないことが条件です。
一方で、家具・家電・衣類・生活用品などの残置物はNGのため、撤去しなければいけません。残すか処分するかは、事前に解
体業者と相談し、契約書に明記しておくことがトラブル回避につながります。
残置物の処分を含めた住宅解体ならビクトリーまで

残置物処理から解体工事まで一括で依頼したい方には、総合対応が可能な業者がおすすめです。ビクトリーでは、住宅解体と同時に残置物処理も承っており、施主の負担を大幅に軽減できます。
POINT
環境省の方針に沿った適正処理を徹底し、廃棄物の分別から搬出・リサイクルまで一貫対応。見積り時に処分範囲を明確化するため、追加費用の心配もありません。住宅解体で残置物の処分にお困りの方は、ぜひビクトリーへご相談ください。
まとめ
住宅解体における残置物処分は、施主の責任で行うべき大切な工程です。家具・家電・生活用品はすべて撤去が必要で、環境省の方針や契約内容を踏まえて適正処理することが求められます。
仕分けから処分先の選択、搬出を計画的に行い、必要に応じて業者に依頼することで滞りなく残置物の処分が可能です。信頼できる解体業者を選べば、残置物処理から工事完了までスムーズに進行できます。安心して解体を進めるために、準備と業者選びを怠らず、残置物を処分しましょう。
総合解体 / 解体事業についてはこちら