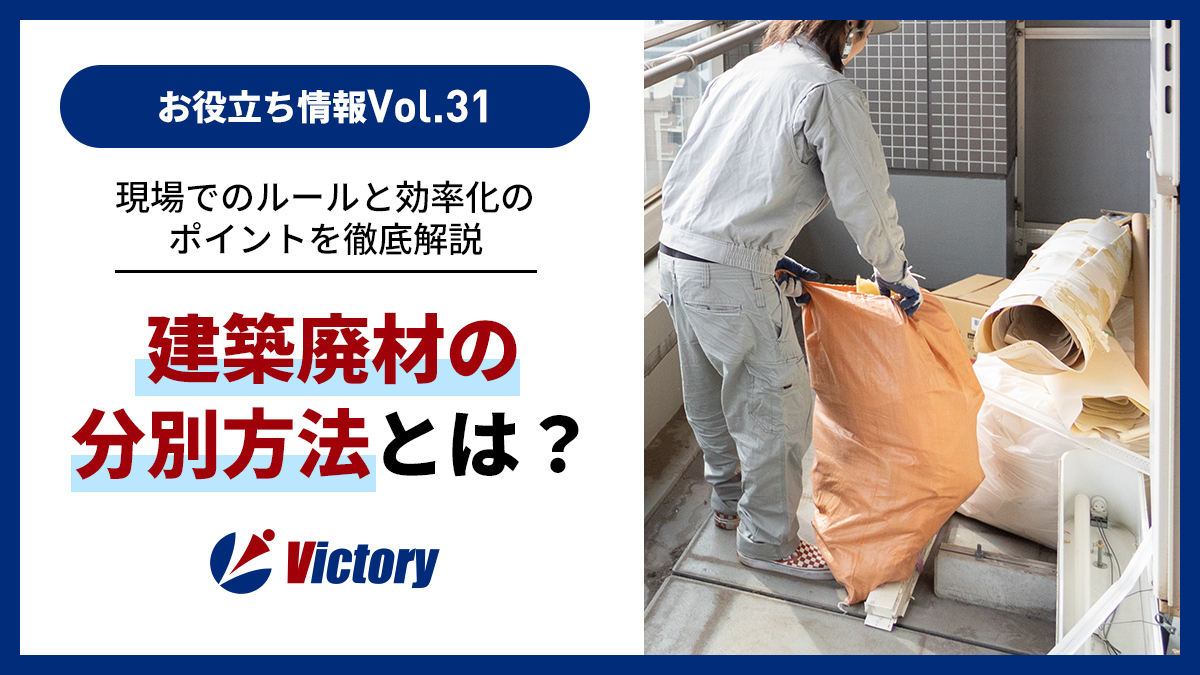木造住宅の解体の流れと手順は?工事の流れや自分でやる場合の注意点などを徹底解説

老朽化した木造住宅を解体したいものの、工事の流れや手順がわからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。解体工事は、手続きや安全対策など多くの工程があり、流れを理解しておくことでトラブルを防げます。
本記事では、木造住宅の解体の流れと手順をわかりやすく解説し、自分で行う場合の注意点も紹介します。木造住宅の解体をどのように進めればいいか、自分で施工する場合の参考になるため、ぜひ最後までご覧ください。
木造住宅の解体が必要になるケース

木造住宅の解体が必要となるのは、主に次の3つの場合です。
- 老朽化や耐震性の問題
- 建て替えや土地活用のため
- 空き家対策や行政指導
ここでは、それぞれのケースごとの木造住宅を解体する必要性を解説します。
老朽化や耐震性の問題
木造住宅の解体が必要な事例で最も多いのが、老朽化と耐震性に起因する理由です。築40年以上の木造住宅では、耐震基準や老朽化が大きな課題になります。特に、1981年以前に建てられた住宅は旧耐震基準に基づいており、地震で倒壊する危険もあります。
POINT
また、柱や基礎が腐食しているとリフォームよりも解体・新築の方が安全で経済的なケースも少なくありません。耐震診断を受けて安全性に問題がある場合は、早めに解体し、崩壊などの事故を防ぐ必要があります。
建て替えや土地活用のため
住み替えや土地活用の一環として、解体を行うケースも少なくありません。古い家を解体して二世帯住宅や賃貸物件を建てる、あるいは駐車場・太陽光発電施設などに転用するなど、活用の幅は広がります。
POINT
建て替えや土地活用をする場合、解体後の土地利用計画を明確にすることで、費用や手続きもスムーズです。こうした理由で解体する際は、不動産会社や建築業者と連携して解体からその後の土地の利用計画を進めると安心です。
空き家対策や行政指導
空き家対策や行政指導なども木造住宅を解体する理由の1つです。近年、空き家の老朽化による倒壊や火災リスクが社会問題化しています。放置された住宅が「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除されるなどの不利益もあります。
POINT
行政からの改善命令や指導を受ける前に、自発的な解体・除却を検討するのが望ましいです。管理が行き届いていない空き家で事故や事件が起きると、持ち主に責任が問われます。そうなる前に解体し、有効に活用することがおすすめです。
木造住宅の解体工事の流れ

木造住宅の解体工事は、事前準備から整地・引き渡しまでの工程を踏む必要があります。ここでは、木造住宅を解体する際の流れを、以下の順序で解説します。
- 事前調査と近隣挨拶
- ライフライン停止と内部撤去
- 屋根・外壁の解体と廃材分別
- 重機による主要構造の解体
- 整地・廃材処理・引き渡し
事前調査と近隣挨拶

工事前には、建物の構造・使用建材・アスベストの有無などを確認する事前調査を行います。この調査によって、必要な機材や作業手順が決まり、正確な見積もりができます。可能であれば発注者も立ち会うことで、より正確な工事が可能です。
調査する際は、同時に近隣住民への挨拶と工事説明も重要です。騒音・振動・粉じんの発生を事前に伝えることで、トラブルを未然に防げます。信頼できる解体業者は、これらの対応も代行してくれるため、依頼時に確認することをおすすめします。
ライフライン停止と内部撤去
解体工事をはじめる前に、電気・ガス・水道・電話回線などのライフラインを停止しなければいけません。特に、ガスは漏洩による火災リスクがあるため、専門業者による閉栓手続きが欠かせません。
ライフラインの停止後は、屋内の建具・畳・配線・断熱材などの内装部分を撤去します。この「内装解体」は手作業で行われ、素材ごとに分別しながら進めるのが一般的です。リサイクルを考慮して丁寧に撤去することで、環境・コストの両面でメリットがあります。
屋根・外壁の解体と廃材分別

内部を撤去したら、建物の外装部分である屋根・外壁を撤去します。瓦やスレート材は手作業で外し、木材や金属部材は素材ごとに分けて処理します。この段階で発生する廃材は、「木くず」「金属くず」「コンクリートがら」など材質ごとに分別回収します。
解体工事では、解体によって発生した廃材は、建設リサイクル法に基づいて処理しなければいけません。その際、マニフェスト(産業廃棄物管理票)も必要なため、適切に処理することが重要です。
重機による主要構造の解体
屋根や壁の撤去が完了したら、いよいよ重機を使って主要構造を解体します。木造住宅の場合、上部から下部に向かって順に壊すのが一般的です。重機オペレーターと作業員が連携し、倒壊リスクを抑えながら慎重に作業を進めます。
作業をする際は、ほこりや破片が飛散しないよう防音・防塵シートでの養生も欠かせません。養生がおろそかになっていると、周辺へ飛散し、近隣トラブルになる恐れがあります。そういったトラブルを避けるためにも、しっかり養生できる解体業者を選ぶことが大切です。
整地・廃材処理・引き渡し
解体が完了したら、地中の基礎や配管などの残存物を撤去し、重機で整地します。表面をならした後、必要に応じて砕石や砂利で地盤を安定させなければいけません。その後、産業廃棄物の搬出・処分を完了し、マニフェスト報告書を受け取ります。
最終的に発注者が現場を確認し、問題がなければ引き渡しと完了報告書の受領で完了です。整地後は速やかに「建物滅失登記」を行い、登記簿から建物情報を削除しなければいけません。
木造住宅を自分で解体できるか

費用節約のため、木造住宅を自分で解体しようと考える人もいます。しかし、個人による解体には多くのリスクが伴います。ここでは、木造住宅を自分で解体するメリットとデメリットや注意点、専門業者に依頼するべき工事を解説します。
DIY解体のメリットとデメリット
DIY解体のメリットは、軽微な部分を自分で撤去することで費用を削減できる点です。たとえば、家具の搬出や一部の内装解体を自分で行えば、数万円程度のコスト削減につながります。
一方で、自分で解体するデメリットは、解体に要する時間・労力・危険性の高さが挙げられます。作業中の事故や近隣トラブルが発生すると、結果的に修繕や補償で余計な費用が発生する場合もあります。
こうしたメリットとデメリットを比較検討して、自分でできる範囲で解体を進めることがおすすめです。
法律上・安全上の注意点
建設リサイクル法では、延床面積80m2を超える建物を解体する場合、自治体への届出が必要です。また、解体作業中の廃棄物は産業廃棄物扱いとなり、一般廃棄物としては廃棄できません。
無届けでの工事や不法投棄が発覚すれば、罰則や行政処分の対象です。さらに、高所や重機を扱う作業は非常に危険です。事故が起きても労災保険は適用されません。安全確保と法令遵守のためにも、無理なDIY解体は避けるべきです。
自分で解体できる範囲と業者依頼の判断基準
自分で行えるのは、家具の搬出・畳の撤去・簡易的な内装解体までが限度です。それ以上の作業は構造上のリスクが高く、専門業者の技術と重機が必要です。業者に依頼する際は、以下の点を確認する必要があります。
- 建設業許可や産業廃棄物収集運搬業の有無
- 見積書の明細の透明性
- 近隣対応の丁寧さ
費用の安さだけで選ぶより、安全性と信頼性を重視することが、結果的に安心につながります。
木造住宅解体を成功させるためのポイント

木造住宅の解体をスムーズに進めるには、業者選びから工事計画までの段取りが重要です。ここでは、解体工事を成功させるために重要な以下の3つのポイントを紹介します。
- 信頼できる解体業者を選ぶ
- 必ず事前に見積もりをとる
- 解体後の土地活用を見据えた計画を立てる
信頼できる解体業者を選ぶ
木造住宅の解体で最も重要なのは、信頼できる解体業者の選定です。資格や許可を持たない業者に依頼すると、不法投棄や近隣トラブルにつながるリスクがあります。選ぶ際は、以下の点の確認が必要です。
- 建設業許可や産業廃棄物収集運搬業の許可の有無
- 実績や口コミ評価の信頼性
- 契約内容や費用明細の透明性
これらが明確な業者は、トラブル対応や安全管理も徹底しています。現地調査時に、担当者の説明が丁寧かどうかも重要な判断材料です。
必ず事前に見積もりをとる

木造住宅の解体費用は、建物の構造・立地・廃材量によって大きく変わります。そのため、1社だけでなく複数業者から相見積もりを取ることが大切です。見積書をチェックする際は、内訳に以下の項目が含まれているか確認しましょう。
- 解体費(重機・人件費)
- 廃棄物処理費・運搬費
- 養生・整地費
- 各種手続き費用
金額が安すぎる場合は、廃棄物処理を不正に行っている可能性もあるため注意が必要です。費用の根拠が明確な業者を選ぶことで、安心して工事を任せられます。
解体後の土地活用を見据えた計画を立てる
解体は「終わり」ではなく、「新しい土地活用のスタート」です。解体前に、更地をどのように利用するかを明確にしておくと、後の工程がスムーズに進みます。たとえば、建て替え予定がある場合は地盤調査や整地の方法をあらかじめ業者に相談しておくと、その後の流れがスムーズです。
POINT
駐車場や賃貸物件、太陽光設置など、目的に応じて地盤の仕上げは異なります。木造住宅解体後の長期的な視点で土地計画を立てることで、無駄な費用を抑え、効果的な活用が可能です。
木造住宅の解体はビクトリーにおまかせ

木造住宅の解体なら、ビクトリーにおまかせください。当社は、木造・鉄骨・RC造などあらゆる構造物の解体に対応し、安全性と環境配慮を両立した施工が可能です。建設リサイクル法に基づく適正処理を徹底し、発生した廃材の再資源化にも取り組んでいます。
また、現地調査・見積もり・届出・近隣対応までワンストップでサポートします。お客様の目的に合わせた最適なプランを提案し、安心・確実な解体を実現します。木造住宅の解体を検討する際は、ビクトリーにご相談ください。
まとめ
この記事では、木造住宅を解体する際の流れや、自分でする際のポイントなどを解説しました。木造住宅の解体は、適切な業者選びと事前準備が成功の鍵です。老朽化や建て替え、空き家対策など目的を明確にし、流れを理解して計画的に進めることが重要です。
安全性・法令遵守・廃棄物処理を徹底した業者なら、安心して任せられます。もし信頼できる解体パートナーをお探しなら、木造住宅の解体経験が豊富なビクトリーへご相談ください。ニーズに合った最適な解体のプランをご提案します。
総合解体 / 解体事業についてはこちら