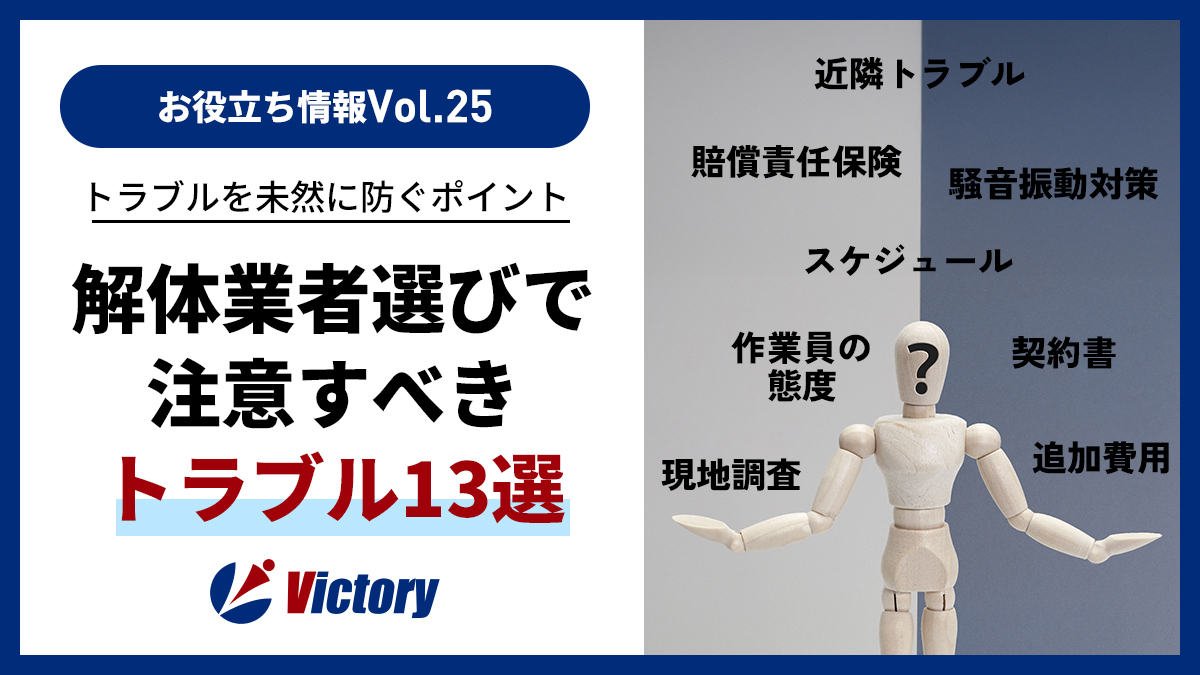建物の解体で注意すべきアスベストとは?工事の流れや注意点を解説

建物の解体を計画する中で、「アスベスト」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。近年の法改正で、アスベスト対策は解体工事において重要なポイントとなりました。事前調査や適切な対応を怠ると、健康被害や法的リスクが発生する可能性もあります。
そこで今回は、解体工事を安全・円滑に進めるためのアスベスト対策の基本や工事の流れ、押さえるべき注意点を詳しく解説します。アスベストを含む建物を安全に解体するための知識が身につくので、ぜひご覧ください。
お電話でのご相談
平日 8:00-18:00
最短即日対応◎メールフォーム
アスベストとは

アスベストとは、天然に産出する鉱物繊維で、建材などに多用されてきました。高い耐熱性・絶縁性が特徴ですが、健康被害が明らかになったため、現在は使用が禁止となっています。ここでは、アスベストについて、以下の2つの点から解説します。
- 別名「石綿」
- アスベストの危険性
別名「石綿」

アスベストは、石綿(いしわた)という別名で呼ばれることもある素材です。繊維状の形状を持つため、非常に細かく空気中に舞いやすい性質があります。断熱性や耐摩擦性に優れ、熱絶縁性や電気絶縁性を有しているため、家庭用品や自動車の材料など幅広い分野で使われました。
また、建物の屋根材や壁材、断熱材などにも幅広く使われた建材でもありました。特に1970〜1980年代の建物には高確率で含まれている場合があります。建物の劣化や解体時には石綿が飛散しやすいため、適切な処置が必要です。
アスベストの危険性
さまざまな優れた性質を持つアスベストには、吸い込むと、重篤な健康被害を引き起こすリスクがあります。そのため、現在は使用禁止になっている素材です。アスベストを吸い込むと、以下のような病を発症する恐れがあります。
- 悪性中脾腫
- 肺がん
- 石綿肺
悪性中脾腫
悪性中皮腫は、アスベスト曝露による代表的な疾患です。胸膜や腹膜などの中皮に発生し、潜伏期間が30〜40年と長い点が特徴です。発症後は進行が早く、治療が難しい場合も多いことから、早期の予防が非常に重要とされています。特に若い時期にアスベストを吸い込んでいると悪性中脾腫を発症する可能性が高いため、若年の作業員は特に注意が必要です。
肺がん
アスベストを長期間吸入することで、肺がんを発症するリスクも高まります。発がん性が明確に認められており、タバコとの併用で発症リスクがさらに増大します。特に、解体作業やリフォーム時は、飛散した繊維を吸わないよう厳重な管理が必要です。アスベストを原因とした肺がんも潜伏期間が長いため、高齢になってから発症することも珍しくありません。
石綿肺
石綿肺は、アスベストを吸入したことによって肺が線維化し、呼吸機能が低下する疾患です。慢性的に進行し、息切れや咳などの症状がみられるようになります。定期的な健康診断と曝露防止策が不可欠です。アスベストを10年以上吸引した人に見られることが多く、アスベストを吸引しなくなっても症状が進行するケースもあります。
解体前にアスベストの事前調査が必要

法改正により、建物解体や改修工事の際には、アスベストの有無を事前調査し報告することが義務付けられました。そのため、専門知識を持つ調査者による適正な診断が必要です。ただし、報告義務のない工事もあります。ここでは、報告が必要な工事とそうでない工事の違いを解説します。
事前調査の報告が義務付けられる建築物
報告が義務付けられるのは、1980年代以前に建築された住宅や商業ビル、公共施設などが主な対象です。具体的には、以下の条件に当てはまる工事では、事前調査の結果を報告しなければいけません。
- 延べ床面積80㎡以上の解体工事
- 改修工事で請負金額が100万円以上の工事
- アスベスト含有が疑われる建材を使用した建築物
POINT
調査の必要性があるか判断が難しい場合は、各自治体に相談してみてください。
報告義務のない工事
アスベストを含有する建物を解体する場合、自治体への調査報告を義務付けられている工事もあります。一方で、次のような工事は報告義務の対象外となります。
- 建築物の修繕や部分的な補修のみをする場合
- 請負金額が100万円未満の小規模工事
- アスベスト含有の可能性がないと認められる建材のみを扱う場合
POINT
ただし、自治体への報告義務がない場合でも、発注者に対しての調査報告は必要です。そのため、解体業者選びの際は、アスベストに対して十分な経験と知識を持った事業者を選ぶことが安全に工事をするためのポイントです。
アスベストが含まれる場合の工事の流れ

アスベストが確認された場合、解体工事は一般の建物よりも慎重な工程で進みます。専門的な事前調査から除去作業、最終的な記録保存まで、厳格なルールに従って工事を実施します。アスベストが含まれる場合の工事の主な流れは、以下の通りです。
- 事前調査
- 官庁への届出
- 工事準備
- アスベストの除去
- 建物の解体
- 作業記録の保存
事前調査
まず、建物のアスベスト含有状況を詳細に調査します。図面や現地確認、建材のサンプリング・分析から、アスベストの有無・含有箇所・使用量を明らかにします。調査結果は、届出や除去作業の計画に直結するため、信頼できる業者による正確な診断が不可欠です。事前調査でアスベストの有無が不明瞭だった場合は、専門家による詳細な調査が必要です。
官庁への届出(※レベル1・2作業に該当する場合)

調査の結果、アスベストが含まれており、レベル1(吹付けアスベスト)またはレベル2(保温材・断熱材などのアスベスト)に該当する作業を伴う場合は、所轄の労働基準監督署や自治体へ事前に届出が義務付けられています。これは、労働安全衛生法や大気汚染防止法などの関連法令に基づく重要な手続きです。
届出には、アスベスト調査結果、除去計画、作業工程、養生・飛散防止措置などの詳細な情報を記載し提出します。
万が一届出がなされていない場合、行政指導や工事の停止などのリスクがあるため、適切な判断と確実な届出が求められます。
POINT
なお、レベル3(アスベスト含有仕上塗材など)に該当する作業では、届出義務はありませんが、飛散防止や適正な処理のための十分な対策が必要です。
工事準備
届出後は、安全対策を徹底して現場準備を進めます。作業区域を養生シートやバリケードで密閉し、周辺への飛散防止措置を講じなければいけません。
レベル1・2に該当する除去作業の場合は、エアシャワーや陰圧除じん装置といった専用設備の導入が義務づけられています。これにより、アスベストが外部に漏れるリスクを極限まで抑えます。また、近隣住民への告知も必要です。
アスベストの除去
準備が完了したら、アスベストを除去します。除去作業は、厚生労働省の指針に基づき、慎重かつ計画的に行わなければいけません。作業区域内で散水などによる湿潤化を徹底し、粉じんの飛散を最小限に抑えながら、アスベストを除去します。取り外した石綿は専用袋に密閉し、特別管理産業廃棄物として適正に処分場まで運搬する必要があります。
建物の解体
アスベスト除去後に、建物本体の解体作業を開始します。安全確認と現場の清掃をした後、重機や人力で解体を進めます。作業の際は、アスベストの残留がないことを確認しながら、作業を進めるのが一般的です。飛散や二次被害を防ぐため、常に現場監督者が管理を徹底しなければいけません。粉塵に紛れていることもあるため、蔓延に注意が必要です。
作業記録の保存
工事終了後は、アスベスト除去や解体の工程記録、廃棄物の処分記録など関連書類を保存します。解体工事そのものに関する記録は3年間、労働者に関する記録は40年間保存が義務付けられています。これらは、後日確認やトラブル対応の際に必要です。万一の指摘や追加調査に備え、記録管理を徹底しなければいけません。
アスベストを含む建物を解体する際の注意点

アスベストを含む建物の解体では、法令遵守と健康被害防止の観点から、通常よりも多くの注意が必要です。以下の点に注意して、解体工事に取り組む必要があります。
- 関係法令に違反すると罰則が科される
- 補助金を利用できる場合がある
関係法令に違反すると罰則が科される
アスベスト関連工事では、労働安全衛生法・大気汚染防止法・廃棄物処理法など、複数の法令を遵守しなければなりません。以下の内容に違反した場合、工事の中断命令や事業者・発注者双方への罰金、刑事責任が問われることもあります。
- 届出や記録保存を怠る
- 適切な除去・処分をしない
- 飛散防止策が不十分
POINT
実際に行政処分や損害賠償請求が発生した事例もあるため、細心の注意が必要です。十分すぎるほどの準備をしてから、工事を開始することが賢明です。
補助金を利用できる場合がある
アスベスト除去や解体には多額の費用が発生することも珍しくありません。そのため、自治体によっては、アスベスト除去工事や廃棄物処分に対して補助金制度を設けている場合があります。
対象となる工事や補助対象金額、申請方法や必要書類は地域や年度で異なります。各自治体のホームページや担当窓口に問い合わせてみてください。賢く補助金を活用することで、経済的な負担を軽減して解体工事ができる可能性があります。
解体時のアスベストに関するよくある質問

建物の解体に伴い、アスベストについて不安や疑問を持つ方は多いものです。ここでは、よく寄せられる質問に専門的な視点でお答えします。
Q.解体でアスベストを取り扱う場合に資格は必要ですか?
A.アスベストを含む建物の解体や除去作業には、法律で定められた資格や講習の修了が必要です。具体的には、「石綿作業主任者技能講習」を修了した有資格者の配置が義務付けられています。さらに、現場作業員も「特別教育」を受けなければなりません。
資格がないまま作業すると法令違反となり、発注者や事業者にも罰則が科されます。アスベストを含む建物の解体や除去作業には、必ず信頼できる専門業者に依頼する必要があります。
Q.アスベストを含む建物を解体する際に使える補助金はありますか?
A.多くの自治体では、アスベスト除去や解体に対する補助金制度が設けられています。たとえば、埼玉県では石綿含有建材の除去工事に対し、最大で工事費用の3分の2かつ600万円の補助金が支給されます。
申請には、工事前の事前調査報告や工事計画書、費用見積書などが必要です。補助内容や条件は自治体ごとに異なるため、工事依頼前に公式サイトや窓口で最新情報を確認してみてください。
解体時のアスベストの処理もビクトリーにおまかせ

アスベストを含む建物の解体・除去は、高度な知識と豊富な経験が求められます。アスベストを含む建物の解体も、ビクトリーでは石綿作業主任者をはじめとする有資格者が現場管理を徹底します。
最新法令に基づき、調査・届出・除去・廃棄物処分までワンストップで対応が可能です。安心・安全を第一に、近隣への配慮や適正な費用提案も行います。アスベストの除去は、ぜひ専門業者であるビクトリーにご相談ください。
まとめ
この記事では、アスベストを含有する建物の解体を解説しました。建物の解体時におけるアスベスト対応は、健康被害の防止や法令順守の観点から極めて重要です。事前調査や官庁への届出、適正な除去作業に補助金の活用など、正しい知識と信頼できる専門業者の選定が不可欠です。今回解説した内容を参考に、アスベストを含む建物の解体を計画してみてください。
アスベストの不安や疑問は、まずはお気軽にビクトリーまでご相談ください。安全・安心な解体工事を全力でサポートいたします。